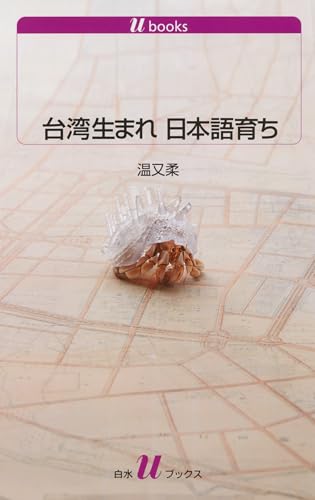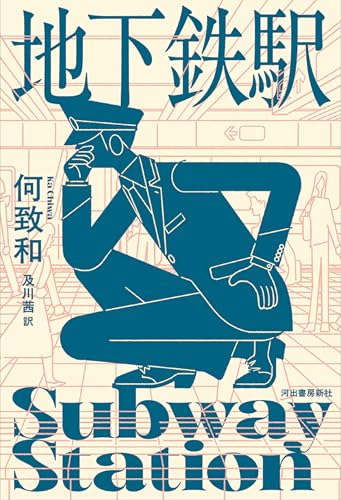知られるように睡眠は非常にだいじである。ことにぼくの場合、もう50歳にもなると徹夜や夜更かしなどで無理をするわけにもいかない。なので今日も今日とてゆっくり眠り、午前7時にシャワーを浴びてその後洗濯機をまわして昨日着ていた服を洗濯し始めた後、7時50分からの英会話のZOOMミーティングに参加する。今日の話題は俗に言う「金縛り」について(身体は眠っているのに脳だけが覚醒して、そのせいで手足が言うことを聞かないという現象の話)だった。そこから話題が幽体離脱やはたまた宇宙人(エイリアン)の目撃談、UFOについて、中国製の介護ロボットについてなど自在に発展してなかなかおもしろいひと時を過ごせた。
その後、今日は遅番なのでグループホームの本家にお邪魔させてもらいそこの食堂を借りて物思いにふける。お供として小川和『日常的な延命』を持ち込みすこし読んだのだけど、いまのぼくの問題意識にピッタリ寄り添うたぐいの本であると見た。これはだいじに読みたい。ただ、以前から書いているように5連勤の疲れがまだ抜けておらず、なんだか脳が不完全燃焼を起こして思考がまとまらずしたがってせっかくの好著との出会いを生産的に活かせず、かえって無為に時間が過ぎてしまった。しょうがないのであきらめる。そんな日もあるのだった。
早目に本家を発ち、図書館に寄りそこでウィル・エルスワース=ジョーンズという耳慣れない方の大判の本『失われたバンクシー』を見つけ、さっそく借りる。そして昼食までの時間にそれをすこしめくってみたのだけど、これもまたなかなかおもしろい。思えばバンクシーのアートとはどう位置づけられるのだろうか。例外もあるけれど、たいていはバンクシーの作品は街路(ストリート)に突如としてあらわれ話題をかっさらうたぐいのもので、つまりはお高く止まった「芸術」とは異なる位相に属する。すくなくともぼくはバンクシーのアートをその質ももちろんさることながら、彼の一挙手一投足じたいが問題をはなつものと見做している。
ゆえに、バンクシーのアートを見るということはそれをいたずらに権威化するということではなく、自分自身でバンクシーのアートのメッセージ性や意義を考え抜く作業をするということなんだろうと思う。もちろん、それは端的に言って非常にめんどくさい(そしてもちろん、そうして考え抜いた結論がバンクシーのアートにまったく似つかわしくないものである可能性、もっと言えば「間違い」にたどり着く可能性もある)。ただ、そんなふうにバンクシーをぼくなりに読み解く作業をとおしてぼくはいろんなことを学ばせてもらったし、これからもそうなんだろう。
その後昼食時になり、この5連勤などでいそがしくて溜まってしまっていたWhatsAppやWeChatなどのメッセージの返事を書いて友だちに送る。その際、国際交流協会をとおして来月おこなわれるイベントの話(ぼくもアシスタントというかボランティアとして参加する)の話をしたりした。英語を学んで10年。前にも書いたけれど、こんなかたちでぼくの夢はすこしずつ実現に向かうのかなあ、と感慨にふけってしまう。まったく予想してなかったことだけど。
それで1時より仕事に入る。そして仕事中、ふと「そもそも、なんであんなにつらい地獄の思いを子どもごころに味わいながら学校に通ったのかなあ」とあれこれ考えてしまった。あくまでぼくの主観から見れば、もちろんぼくにもいたらないところはあったのだろうけれどなんだかクラスメイトが急にパタパタとぼくの元から去っていって嫌うようになったので、悪い夢を見ているような不条理な気分だったことを思い出す。そこから嫌われる原因をぼくなりにあぶり出そうとしたり、なんとかして感情の「言語化」に励んだりもした。そのクセがいまでも抜けていないということなんだろうと思う。
ぼくのことを嫌う理由がまったくもってわからない……それは(学問の安易な援用・濫用になるが)「空気」「雰囲気」でぼくが嫌われる存在として位置づけられ、そこからぼくになんら釈明の余地もあたえられず、人間関係が固定された環境でただただスケープゴート(生贄)になるしかないということを意味するのだった。そうした洗礼を子どもの頃に浴びたせいか、その後大学生になっていじめと無縁に生きられた環境であっても自分が嫌われているのではないかとかいう不信感にさいなまれて、エラい目に遭ったことを思い出す。
そんなことを英語でいつものようにメモパッドに書きつけていく。スケープゴートならばそれはそれでしょうがないと、そこから「剽軽(ひょうきん)」を演じて生き延びようとしたこともいい思い出である。40代になってやっと、もちろん大々的なカリスマになるなんてことは望めないにせよ、自分のまま・ありのままで生きることがいちばん疲れないしそれに信頼できる人を見分けられるリトマス試験紙にもなるとわかってきたのだった。ああ、そんなことをわかるのに40年もかかった。長かったなあ。
そんなこんなで仕事をこなし、そして帰宅してしばしくつろいでこの日記を書いて、そして1日が終わった。ちなみにいまも昨日と同じようにダニエル・ラノワの楽曲群を聴いている。前にハマったブルース・スプリングスティーン『ネブラスカ』といい、こういう路線が病みつきになるようだ。